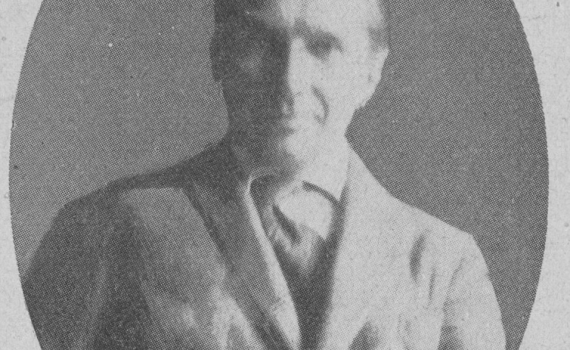
なぜまだ世界初演が行われないのでしょうか?
Category : 公演 | Auff jp
https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Dahms
Hamburg Staatsbibliothek https://resolver.sub.uni-hamburg.de/kitodo/PPN774616555_0016
[pgc_simply_gallery id=”221″]
ウォルター・ダムスは1912年にこのオペラについての詳細な記事を書きました。
まだ完全なステージパフォーマンスが行われていない理由(まだ 2026 年!)は、次のように説明されています。
ゲプファルトの「ザラストロ」のピアノ・リダクション版を初めて手に取った時、これほどまでにシンプルで明快、そして曖昧さのない作品を現代に提示するという作者の大胆さに衝撃を受けました。確かにこの作品は1891年のモーツァルト生誕記念日に構想・作曲されました。しかし、不運な混乱(とりわけ大規模な印刷業者ストライキ)により、ドレスデンとプラハでの予定されていた演奏は、当時実現しませんでした。そして翌年には、既に手遅れでした。こうして「ザラストロ」は未だに未演奏のままです(著者注: 1912年)。もしそれが、お気に入りの新聞によって自国の芸術家たちのことをほとんど知らない善良なドイツ人たちの手に委ねられていたら、この作品は永遠に未演奏のままだったかもしれません。しかし、極めて一方的で利己的なジャーナリズムが、創造的な知性と騙されやすい大衆の間に築いてきた惰性と悪意の壁を、いつか破ることができなければ、それは残念なことです。この試みは、教訓的で将来性に富む、価値のあるものとなるでしょう。
カール・ゲプファルトの音楽劇「ザラストロ」
ウォルター・ダムズ著
近頃、「魔笛 第2部」という作品を聞いて、耳をそばだてない人がいるだろうか? モーツァルトは現代の音楽的危機の救世主、現代の非生産性の砂漠から抜け出す先駆者として、盛んに語られ、書かれてきた。「モーツァルトに戻れ!」と人々は叫んだ。ヴァインガルトナーは言った。「いや、モーツァルトへ!」 どのような解釈をしようとも、確かなことが一つある。それは、音楽と演劇芸術の更なる発展は決して「ワーグナーを超える」ことではなく、稀有で永続的、そして同時に新しいものを創造しようとする舞台作曲家は、ワーグナー以前の段階から出発しなければならないということだ。なぜなら、偉大で崇高な芸術という目標へと至る、未踏の道がまだ数多く残されているからだ。
ゲプファルトの「ザラストロ」のピアノ楽譜を初めて手に取った時、これほどまでにシンプルで明快、そして曖昧さのない作品を現代に提示するという作曲家の大胆さに衝撃を受けました。確かにこの作品は1891年のモーツァルト生誕記念日に構想・作曲されました。しかし、最も不運な混乱(とりわけ大規模な印刷工ストライキ)により、当時予定されていたドレスデンとプラハでの演奏は実現しませんでした。そして翌年には、既に手遅れでした。こうして「ザラストロ」は未だに未演奏のままです。もし、お気に入りの新聞によって芸術家たちの情報をほとんど得られない善良なドイツ人たちの手に委ねられていたら、この作品は永遠に未演奏のままだったかもしれません。しかし、極めて一方的で利己的なジャーナリズムが芸術家たちと騙されやすい大衆の間に築き上げた惰性と悪意の壁が、いつか破られないとしたら、それは残念なことでしょう。この試みは価値があり、有益で、同時に将来有望なものとなるだろう。
「ザラストロ」は、初めて聴いた瞬間から深く、忘れられない印象を残しました。私は何度もこの作品に足を踏み入れ、興味はどんどん深まっていきました。ついに、現代が愛し、奨励するものとは全く異なるものを目指した作品がここにありました。ここでは、人間の根源的な感情は(通俗的なヴェリストやそのドイツ人追随者たちのように)嫌悪されるべきものではなく、むしろ洗練されるべきものなのです。純粋で、地に足の着いた、健全な何か、つまり、ドイツ的なものが、力強く、感傷的で、涙を誘う至福の形で、まるで病的な言葉と音楽の爆発のように、私たちに語りかけてくるのです。だからこそ、私は今、この作品に警告の言葉を記そうとしているのです。音楽家として、また批評家として、この作品は高貴なものを受け入れるすべての人々にも影響を与えるに違いないという、揺るぎない確信を得たからです。
全体が象徴的だ――光と闇、善と悪の闘争。モーツァルトの「魔笛」にもこの傾向があった。それは、当時のウィーンで事情を知る者にとっては理解しやすい抗議であり、あらゆる分野における無気力、堕落、そして良心の抑圧に対するものだった。人道的な空想は一切なく、普遍的な人類の兄弟愛という理想を訴えようとした。(しかし、間近に迫っていたフランス革命は、これに激しい不協和音をもたらした。これも一種の兄弟愛ではあったが、別の種類のものだった!)当時、目指されていたのは運命の試練によって清められた登場人物を描くことだった。火と水は単なる象徴に過ぎなかった。しかし、「魔笛」では、光と闇、ザラストロと夜の女王の闘争は描かれていない。終楽章は、闘争と争いの時代である来るべき時代を指し示している。
ゲーテは、魔笛の第二部、ザラストロのドラマをオペラのテキストとして企画・執筆した人物である。ゴットフリート・シュトンメルが詩を書いたゲプファルトの作品は、この土台の上に成り立っている。ゲーテによる魔笛の続編は正当なものだった。大まかに光と闇に象徴される、相反する二つの自然の力の間の戦いは、どこかの時点で決着をつける必要があった。ゲーテのアウトラインは、ゲプファルトとシュトンメルに劇的な指針を与えた。モーツァルトの音楽は、特定のメロディーとモチーフにおいて、特定の箇所で保持する必要があった。そして、その結果は和解的なものでなければならなかった。愛が憎しみに打ち勝つ必要があったのだ。ゲーテが意図した対立を通して、フリーメーソンの思想を具体化することも同様に必要だった。ゲーテによる魔笛の続編の正当性については、疑いの余地はない。ゲップファルト・シュトムメルの作業が完璧に遂行され、述べられた目標が達成されるのを目撃したとき、人はそれを無条件に、そして喜んで肯定するだろう。
『ザラストロ』を考察すると、各幕の構成に、その本質において独特の要素が込められていることがわかる。第一幕は序幕で、この劇の様々な世界、すなわち善の世界(ザラストロ)、悪の世界(夜の女王)、そして原始的人類の世界(パパゲーノ)へと私たちを導く。『魔笛序曲』の荘厳な導入部の後、司祭たちの集会に幕が上がる。彼らは毎年、兄弟の一人をこの世に送り出し、人類の苦しみと喜びを目の当たりにする。地上の巡礼者は清らかに帰還し、今度はその運命は彼らの指導者であるザラストロ自身に委ねられる。彼はこの言葉に特別なヒントを見出す。「神は危険にさらされている!」彼は、重大で偉大な使命が待ち受けていることを知る。宿敵、夜の女王、原始的悪を克服しなければならない。それを成し遂げられるのは彼だけである。なぜなら、彼は高次の精神修養によって彼女の意図を見抜くが、彼女は彼の意図を見抜くことができないからである。荘厳で真摯な雰囲気が、この場面全体に漂っている。持続的なリズム、澄んだハーモニー、そして深く魂を揺さぶるメロディーが、音楽全体を包み込んでいる。ここで既に明らかなのは、「ザラストロ」がモーツァルトのオペラと同じ意味で声楽オペラであるということ。そして、これがこの作品が現代オペラ文学において特別な地位を占めている理由でもある。オーケストラは決定的な決定権を握っているのではなく、音楽的な出来事が展開される場、いわば土台を提供しているに過ぎないのだ。
最初の変身は、夜の女王の領域へと私たちを導きます。対照的な人物描写です。軽快なリズムは、この領域に蔓延する些細な不安を即座に伝えます。ザラストロと同様に、女王も戦友たちに囲まれて描かれます。『魔笛』で娘パミーナを逃がし、今では母に仕え、愛するムーア人モノスタトスは、光の領域への復讐が本格化していると女王に報告します。タミーノとパミーナの子、王の息子は、黄金の棺に閉じ込められており、その蓋は彼らの闇の力によってのみ開けられます。象徴的に、新しい時代は光を恐れる精霊によって奴隷化されています。女王の勝利の雄叫びは、高貴なザラストロに対する彼女の内なる反感を露わにします。彼女に対する彼の戦いは、なんと正当なものでしょう!
第二の変身では、タミーノとパミーナが愛する子を心配する親としての姿が描かれる。タミーノは我が子への不安を募らせ、母である夜の女王の影響下へと逆戻りする。夜の女王は、タミーノにザラストロへの復讐を勧める。しかし、これはザラストロにとって誘惑となり、ザラストロはタミーノに将来の偉大な使命を約束して慰める。棺を容赦なく運ぶタミーノの姿に寄り添う女声合唱団の優しい叙情性から、誘惑の場面の音楽は力強く盛り上がり、壮大で原始的な司祭合唱「光に抗う者は誰か?」へと繋がる。
第三の変身は、パパゲーノとパパゲーナに体現された、奔放な自然人の生活と営みを私たちに提示します。子供たちの陽気な喧騒の中、喜びと冗談に満ちた中で、神々からの贈り物であるオーロラ姫の誕生が起こります。彼女は民衆の子であり、公家の息子を救う運命にあります。この変身には、美しく静謐な音楽が伴奏します。モーツァルト風の旋律がいくつも登場します。人生の盛衰が鮮やかに、尽きることなく、そしてシンプルでありながら効果的な確かな筆致で流れていきます。
第一幕は劇の展開を担っていたが、第二幕は敵対勢力の爆発によって劇的な効果のクライマックスを迎える。神の召命に忠実に、ザラストロは地上の旅路を歩む。そこで彼は宿敵と遭遇する。光と闇という二つの自然の力の運命が決する。王妃はこの放浪者を認識できない。未知の魔力に圧倒され、彼への激しい愛に燃え上がる。彼女はザラストロを自分の目的のために取り込もうとするが、その根底にはザラストロの破滅が隠されている。ザラストロはついに、王妃が王の息子フィーバスを黄金の棺から解放し、蘇らせると誓った時、ザラストロを抹殺する彼女の協力を承諾する。ザラストロは王妃を打ち負かし、「新時代」をもたらすためには犠牲を払わなければならないことを悟る。彼の人格と告白に宿る倫理的な力は素晴らしい。ゲプファルトの音楽は、詩人と同様に、この見事な演技を構築し、遂行する上で成功を収めている。彼は完全に自身の才能のみを引き出し、旋律と特徴的な創意工夫の源泉は尽きることがない。簡潔な筆致で、彼は対照的な響きを巧みに表現する。彼の音楽言語は劇的に力強く、心に深く刻まれると同時に、全く独特で新しい。感情表現における彼の自信は、随所に見て取れる。特に注目すべきは、夜の女王が勝利を収めたかのように、劇中初めてコロラトゥーラに耽る様子だ。まるで内なる必然から生まれたかのように。ここでコロラトゥーラは真に表現手段であり、真に必要かつ緊張を和らげる手段なのだ。
第三幕の効果は不均一である。これは、必要な解決が積み重なった結果である。劇文学では稀なことだが、ここでは、対立の継続と解決に大きく関わる新登場人物(オーロラとフィーバス)が、第三幕でのみ登場する。当然のことながら、第三幕は主にモーツァルトのモチーフで構成されている。モーツァルトの引用は、ゲーテの楽譜によって部分的に義務付けられている。したがって、オーロラは『魔笛』のグロッケンシュピールの音楽とともに登場する。ここではモーツァルトの音以外には何も聞こえないため、正当化する必要はない。個々の曲において、ゲプファールトはモーツァルトが頻繁に用いたロンド形式を用いている。彼はその様式にとらわれなければならなかった。モーツァルトの音楽を引用することで、彼が物事を単純で安易なものにしたなどと言うべきではない。むしろ、作品全体を崩壊させないために、自身の感性をモーツァルトの様式と精神に適応させることは、途方もない困難を伴った。彼は引用部分を独自の創作で置き換えることもできただろう。しかし、彼はモーツァルトの表現こそが、その特定の箇所において唯一可能な表現であると正しく判断した。
最初の場面は、森の中の原始的な人々へと私たちを連れ戻します。ここでオーロラはフォイボスを解放し、神々が人類に与えたプロメテウス的な賜物を回復させます。物語はクライマックスを迎え、二人の象徴的な人物による最も親密な愛の場面へと移ります。続いて、魅力的で独特のバレエ音楽に彩られた、いわばバーレスクの場面、パンフェストが展開されます。
最初の変身は、タミーノの王宮における宮廷生活の一端を描いています。紳士淑女たちが、最新のニュースを巡って口論しています。この不毛な議論は、まさに最新のニュース、すなわち、救われた王子フォイボスがオーロラ姫と共に入場するという知らせによって終わりを迎えます。こうして終わりの始まりが訪れます。新たな時代が到来するのです。ゲプファルトは、廷臣たちの会話に心地よい響きを見出し、音楽的ユーモアの達人としての才能を遺憾なく発揮しています。
劇は、開放的な変容を経てフィナーレへと導かれる。ここでは、若い王子夫妻の登場を喜ぶ歓喜と、ザラストロの死を悼む司祭たちの悲しみの間に、最も印象的な対比が生まれる。この二つの場面は、モーツァルトの影響を受けたモチーフ、すなわち『魔笛』終楽章の歓喜に満ちた合唱と『火と水の音楽 ハ短調』によってのみ表現可能であった。夜の女王の登場など、場面が進むにつれて、彼女もまた勝利と歓喜を祝っているかのように見え、ゲプファルトは独自の特徴的なアクセントを見出している。場面は破局へと発展する。女王は死んだ敵に会うことを要求し、「もし私の王国が滅びたら!」と叫ぶ。タミーノは彼女をザラストロの石棺へと導く。彼女は死体の中に放浪者を見付け、意識を失う。一方、モーツァルトの不朽の名曲「おお、イシスとオシリス」が、司祭たちから一斉に響き渡り、ザラストロの死後もなお彼の精神を体現し続けることを誓う。自らの敗北という恐ろしい現実に打ちひしがれた王妃は、崇高な愛の絆に結ばれたいという熱烈な願いを表明するが、司祭たちに憤慨して拒絶される。苦悩のあまり、王妃は変貌したザラストロ(敵であり友でもある)に、和解と願いの成就のしるしを求め、願いは叶う。すると、一人の天才が現れ、平和の掌で王妃に触れ、永遠の平和の領域へと導く。ザラストロと王妃はドームの中で結ばれる。愛が憎しみに打ち勝ち、あらゆる悪が消滅したのだ。王族と民衆は、全く異なる高揚感とともに、愛による解放の歓喜の合唱に加わる。
ゲプファルト=シュトンメルの『ザラストロ』は、倫理的な意図と純粋で偉大な意志の作品としてその真価を発揮しています。その意志に見合うだけの力強さは、詩と音楽に紛れもなく表れています。ドイツのオペラハウスは、このように真摯で美しく完成された作品が必ず成功を収めるよう、万全を期さなければなりません。崇高な理念、構想と演奏の簡潔さと力強さにおいて並外れた作品、内なる簡潔さと真実性によって現代創作において類まれな地位を占める作品を、輝かしい舞台へと昇華させるのは、彼らの責任です。そして、この作品は――私は固く確信していますが――常に深く、忘れられない印象を残すでしょう。ゲプファルトの『ザラストロ』で幕を開けるドイツの舞台は、真の芸術的偉業という名声を得るでしょう。